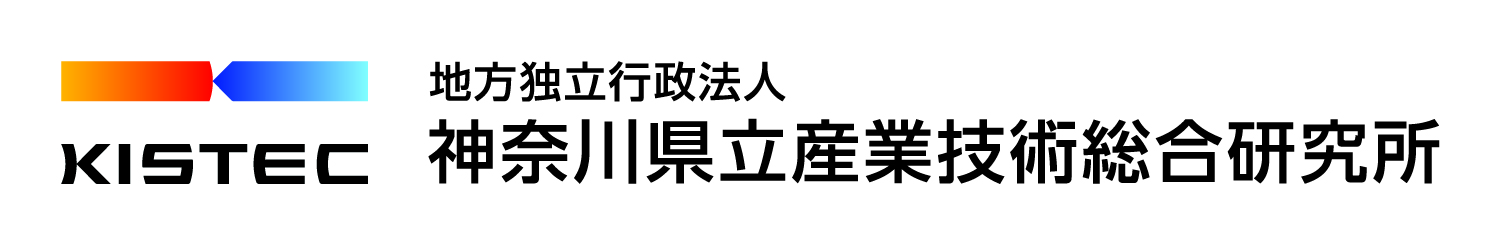【プレスリリース】加齢による骨髄代謝・血流動態の変容を起因とした造血幹細胞生着不全の機序を解明
ポイント
・ 骨髄では血球細胞により産生されるアセチルコリンを起点とした一酸化窒素 (NO) シグナル経路(注1)によって血流が保たれており、加齢によりその機能低下が見られることを明らかにしました。
・骨髄では血流による類洞血管内皮細胞 (注2) の活性化により、移植した造血幹細胞 (HSC) (注3) の骨髄への生着効率 (注4) が維持されていることが示されました。
・ 高齢個体で低下したHSCの生着効率は、加齢により減弱するNOシグナル経路の再活性化や、骨髄類洞血管の活性化により改善が見込まれる可能性が示されました
概要
HSC移植時のHSCの生着率は加齢に伴い低下することが知られていますがその要因は明らかではありませんでした。東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野および国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 造血システム研究部の田久保 圭誉教授・部長、同部の森川 隆之上級研究員ら、神奈川県立産業技術総合研究所の原口美帆研究員らの研究グループは、この要因として骨髄の局所血流・代謝に着目したところ、加齢により血流の減少に加え、血管拡張を担うアセチルコリンや一酸化窒素 (NO) を介するシグナル経路の減弱が認められました。またこのとき血液と血管壁の間に血流によって生じる力、ずり応力(注5)も、骨髄類洞血管で加齢により低下することがわかりました。そこでずり応力のHSCの骨髄への生着における役割を検証したところ、生着において重要な過程である骨髄でのHSCの血管外遊走の効率とずり応力との間での相関を示す結果が得られました。またずり応力を感知する受容体Piezo1(注6)の薬理的な活性化によって血管外遊走の効率が回復しました。さらに高齢マウスに移植したHSCの生着率は、NOの投与や、Piezo1の活性化などによって短期から中、長期にわたって改善が認められました。これらの結果から、移植後HSCの生着効率の加齢による低下は、アセチルコリン-NOシグナル経路の加齢変化が一因となっていることが示され、同シグナル経路が高齢個体での移植効率の改善の向けた有効な治療標的となりうることが期待されています。本研究成果は、2025年7月1日付で学術誌Nature Communicationsに掲載されました。
お問い合わせ
記者発表資料よりお問い合わせ先をご確認ください。