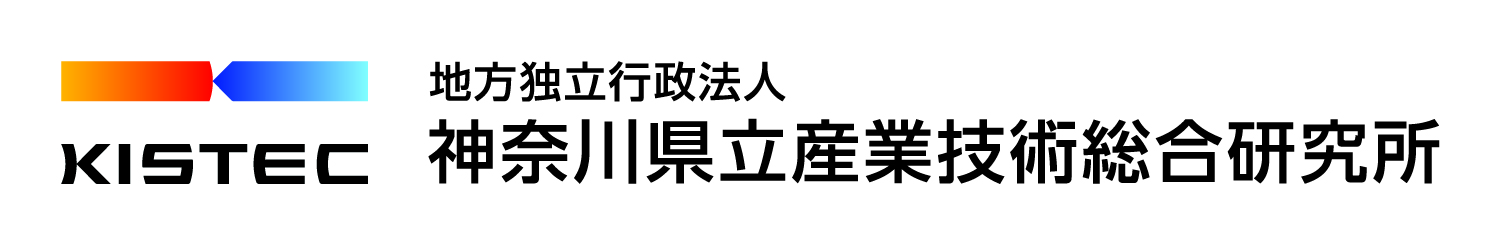徐脈性不整脈の再生医療プロジェクト

徐脈性不整脈の再生医療プロジェクトでは、ヒトiPS細胞を用いてペースメーカ細胞を含むオルガノイドを効率よく作製し、徐脈性不整脈患者の心臓に移植することで、人工ペースメーカ植え込み治療に頼らない、徐脈性不整脈に対する再生治療法の開発を目指します。
期間
- (戦略的研究シーズ育成事業)「徐脈性不整脈の革新的細胞移植治療開発」 2023年4月~2025年3月
- (有望シーズ展開事業)「徐脈性不整脈の再生医療」プロジェクト 2025年4月~
実施場所
川崎生命科学・環境研究センター(LiSE) 神奈川県川崎市川崎区殿町
研究の背景と目的
洞不全症候群や房室ブロック等の徐脈性不整脈は、ペースメーカの役割を担う細胞がさまざまな原因により傷害されることにより生じる。重症なケースでは、心不全症状や脳虚血症状が生じるため、一般的に人工ペースメーカ植え込み術が行われていますが、定期的な電池交換やリードトラブル、感染症、自律神経に対する不応答等、様々な課題が存在します。
人工ペースメーカの市場は大きく、国内のみで2000億円規模、世界では約70億米ドルとされていますが、本邦における人工ペースメーカは100%海外からの輸入に依存しており、医療機器の貿易赤字の一因となっています。
これまでの長年研究において、ペースメーカ細胞の作製法(unpublished)、心筋細胞の純化精製法(Cell Stem Cell 2013, Cell Metab 2016, iScience 2020)、心筋細胞の大量培養法(Stem Cell Reports 2017, iScience 2021)、臨床グレード培養法(Circulation 2024)、移植細胞の品質評価法(Stem Cell Reports 2023)、オルガノイド・組織作製法(Cell Reports Methods 2023, Biomaterials 2023)、移植グラフト評価法(iScience 2024)等が確立できたことから、本プロジェクトでは、移植後に拒絶反応が起こりにくいように遺伝子改変を行った低免疫原性ヒトiPS細胞から、臨床グレードの高純度ペースメーカオルガノイドを作製した後に、徐脈性不整脈モデル動物の心臓に移植し、有効性や安全性を評価することで、『徐脈性不整脈に対する新たな再生治療法の開発』を目指します(図1)。
心臓ペースメーカオルガノイド移植治療が開発できれば、人工ペースメーカ植え込み術が抱える医学的な課題を解決するとともに、海外に依存し、貿易赤字の一因となっている人工ペースメーカへの依存からの脱却につながることが期待されます。

研究内容
1.ペースメーカオルガノイドの製造と特性解析
長年かけて開発してきた臨床グレードの培養法を用いることで、遺伝子改変(低免疫原性)ヒトiPS細胞株から臨床グレードのペースメーカ細胞を効率よく作製するためのプロトコールを決定します。また、低免疫原性臨床グレードiPS細胞から作製したペースメーカ細胞を用いてペースメーカオルガノイドを作製し、従来の心室筋細胞との特性を比較します(図2)。

ペースメーカ細胞ではSHOX2を発現しており、拍動数が1分間に100回以上と、心室筋細胞に比べて顕著に高いことを確認しています。
2.ペースメーカオルガノイドの品質評価
移植後の安全性および有効性を担保するために必要となる品質規格項目を設定し、ヒトiPS細胞から作製したペースメーカオルガノイドの適切な品質評価法を確立します。
3.非臨床試験 (安全性・有効性に関して)
臨床応用を見据えて、遺伝子改変(低免疫原性)ヒトiPS細胞由来臨床グレードペースメーカオルガノイドを免疫不全マウスの皮下および心臓に移植し、腫瘍形成を来たさないか、長期生着が可能であるかを確認します(図3)。また、心臓に移植されたペースメーカオルガノイドに栄養を供給する血管系が構築されるか、移植後長期間に渡ってペースメーカ細胞としての性質を維持しているかを評価します。さらに、ヒトiPS細胞由来ペースメーカオルガノイドを中大型動物における徐脈性不整脈モデルに移植することにより、徐脈性不整脈が改善されるか否かを確認します。

ヒトiPS細胞から作製したペースメーカオルガノイドを免疫不全マウスの心臓に移植し、長期に渡って生着していることを確認しています。
4.非臨床試験 (移植法に関して)
中大型動物を用いた検討において、ヒトiPS細胞由来ペースメーカオルガノイドを移植する際の適切な方法を決定します。