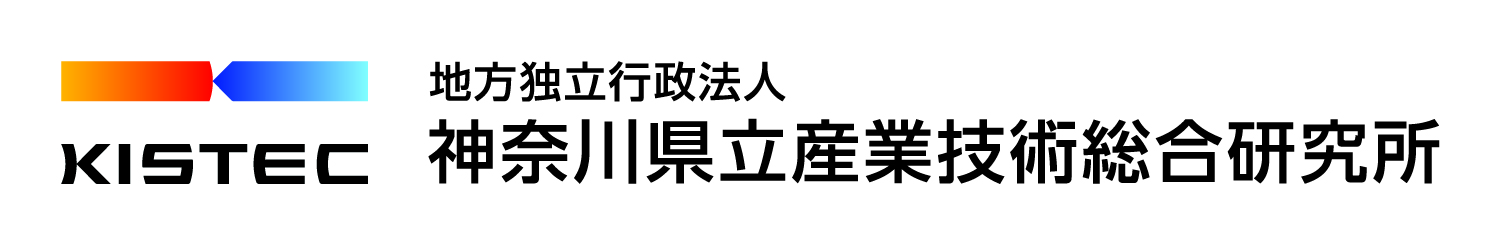社会実装を目指すマイクロ流体デバイス
~フロー合成と生体・環境計測への応用~
募集を終了いたしました。たくさんのお申し込みをありがとうございました。

日時
2025年10月21日 (火)・22日 (水)10:00~16:50
定員
20名(先着順にて承ります。)
受講料
| 区 分 | 全日程 | |
|---|---|---|
| 全日程 | A 一般 | 49,000円 |
| B KISTEC パートナー団体会員 C 神奈川県内中小企業 | 39,200円 | |
| D C以外の神奈川県内企業 E 神奈川県内在住の個人の方 | 44,100円 | |
| 1日受講 | 29,000円 | |
※後援・協賛学会会員様の割引がございます。お問い合わせ下さい。
会場
かながわサイエンスパーク内講義室(川崎市高津区坂戸3-2-1)
Map・アクセス詳細はこちらからご確認ください。(別ページが開きます)
- JR南武線「武蔵溝ノ口」・東急田園都市線「溝の口」下車 シャトルバス 5 分
- JR 新横浜駅より東急バス(有料)直行「溝の口駅」行き30 分 「高津中学校入口」下車徒歩3分 東急バスのアクセスはこちら(外部サイトが開きます)
※感染症対策を実施の上で開催いたします。 感染症対策の詳細はこちらからご確認ください。(別ベージが開きます)
対象者(このような方にお薦めいたします)
≫企業、研究機関に所属し、以下の技術や事業の開発に携わる方。
- 超小型センサ、バイオチップ
- 創薬スクリーニング、細胞医療研究
- エレクトロニクスデバイスの設計、開発、製造、実装
- 半導体関連技術、精密微細加工
- 検査・化学分析等(食品、畜産関係など)
- 紙、繊維、ポリマーなどの新素材開発とその用途探索
カリキュラム
10月21日(火)
10:00~10:30 オリエンテーション

マイクロ流体デバイスの歴史と現在のホットトピックス
北海道大学 大学院工学研究院 生物機能高分子部門
教授 渡慶次 学氏
マイクロ流体デバイスの歴史を俯瞰するとともに、現在のホットトピックスについて紹介します。マイクロ流体デバイスは、当初は、分析や診断がメインのターゲットでしたが、現在はライフサイエンス研究や物質生産などさまざまな用途で使用されています。ここではそれらについて概説します。
10:35~12:20

フロー合成の基礎と応用
北海道大学 大学院理学研究院化学部門 有機反応論研究室
教授 永木 愛一郎 氏
合成化学の常識がフローマイクロリアクターによって大きく変貌をとげ、従来の合成化学が大きく変わろうとしている。フローマイクロリアクターによって提供されるミクロな反応場は、化学反応そのものに本質的な影響を与えるためである。本セミナーでは、フローマイクロリアクター合成の基礎、研究・開発によるフラスコでは不可能な高速合成の事例について、今後の展望を含め紹介したい。
13:20~15:05
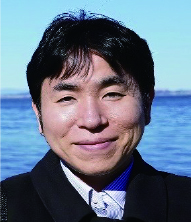
実践的活用を指向した超分子化学センサ
東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門
准教授 南 豪 氏
1967年のクラウンエーテルの報告以来、分子認識化学・超分子化学は非常に精力的に研究され、本分野では2度にわたってノーベル化学賞が授与されている。一方、身の回りを見てみると、人工分子認識材料を活用した化学センサは普及しているとは言い難い。それはなぜだろうか。本講義では、発表者がこれまでに取り組んできた実践的活用を指向した超分子化学センシングについて紹介する。
15:20~16:50

エクソソーム解析とリキッドバイオプシーへの展開
東京科学大学 生命理工学院
教授 安井 隆雄 氏
マイクロ流体デバイスは、従来のチャンネル構造に限らず、セルロースナノファイバーシートのような多孔質材料においても、液体の局所的な輸送や制御といったマイクロ流体的機能を発揮し、リキッドバイオプシーにおけるエクソソームの取り扱いに大きく貢献しています。本講義では、こうしたマイクロ流体的機能を活用したエクソソーム解析と、そのリキッドバイオプシーへの応用展開についてお話しします。
10月22日(水)
10:00~11:40

マイクロ流体デバイスの新たな展開
北海道大学 大学院工学研究院 生物機能高分子部門
教授 渡慶次 学氏
現在のホットトピックスの中から、社会実装が実現している(あるいは実現しつつある)紙デバイスおよび脂質ナノ粒子の応用について紹介します。紙デバイスを利用した土壌診断や乳牛の妊娠診断、神経剤検知、大麻成分分析などと、脂質ナノ粒子を利用したワクチンおよび化粧品などの例についてお話しします。
12:40~14:10

ナノポアによる1細菌・1ウイルス検出
情報通信インフラとしてのスマートフォン+マイクロ流体デバイスで迅速化する公衆衛生管理
大阪大学 産業科学研究所
教授 谷口 正輝 氏
スマートフォンに、電気デバイスとマイクロ流体デバイスの機能を組み合わせて搭載し、 1 個単位で細菌やウイルスを検出 ・ 識別する新たな手法の開発状況について解説します。 取得したデータを AI を用いて解析し、感染予防に役立てるなど、 社会実装に向けた展望をお話しします。
14:25~15:55

分解性材料を用いた生体・環境ワイヤレスモニタリングセンサ
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
教授 尾上 弘晃 氏
本講演では、消化管の状態をモニタリングするための可食カプセルセンサと、スマート農業のための土壌環境の計測システムについて紹介します。本デバイスは無線通信のためにスプリットリング共振器を含め全ての要素が安全な分解性材料で構成されています。
16:10~16:50 質疑応答・ディスカッション
カリキュラム編成者からのメッセージ
マイクロフルイディクス研究が国内で本格化してから約30年。現在、この分野は「セカンドステージ」へと移行しつつあります。超微量物質の検出を可能にするLab-on-a-chip技術は、検出・計測・データ取得を一体化したシステムの構築によって、社会実装を目指す動きが加速しています。デバイス作製技術も進化し、多様化しています。従来のガラスやプラスチック基板を用いた半導体加工技術に加え、紙と印刷技術を活用した簡便なデバイス、さらには電源を搭載した3次元構造の電気化学センサチップなど、新しいアプローチが次々と生まれています。
また、化学合成分野ではマイクロリアクターによるフロー合成の実用化が進んでおり、低コスト・高効率であることに加え、より精密な合成が求められるバイオ医薬や医療分野での応用が期待されています。
本講座では、マイクロ流体デバイスの最新の開発動向と社会実装の進展について概説するとともに、化学合成・創薬・化学分析・ヘルスケアといった分野での注目の開発事例を詳しく紹介します。特に、サンプル導入などのデバイスとのインターフェースなどの技術との連携にも着目し、社会実装が進むマイクロ流体デバイスシステムとその関連技術について掘り下げていきます。
「実用」に適したマイクロ流体デバイスとは何か?どの方向に開発を進めるべきか?本講座が、皆さんとともに未来を考える場となることを願っています。
北海道大学 大学院工学研究院 生物機能高分子部門
教授 渡慶次 学
主催
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)
後援・協賛
川崎商工会議所 (株)ケイエスピー (ほか申請中)
お問い合わせ
人材育成部 教育研修課 教育研修グループ
TEL:044-819-2033
以下お問い合わせフォームをご利用の場合は、
「講座・研修に関するお問い合わせ」をお選びください。